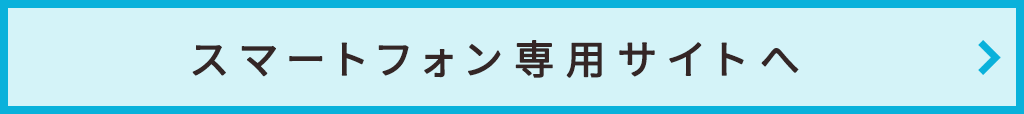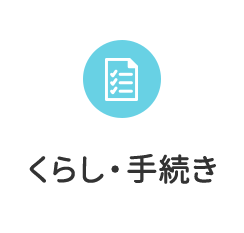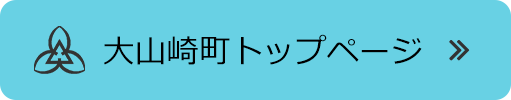平成30年度から都市計画税を導入しています
将来にわたる安心・安全なまちづくりに向けて、平成30年度から都市計画税を導入しています,
平成29年8月から9月にかけて開催されました平成29年町議会第3回定例会で、次のことが決定されました。
*税率は0.1%
*適正管理のための「基金」を新たに設置
1.都市計画税をめぐる経過
都市部の自治体では、それぞれの自治体において、都市計画を定め、その計画に基づいて都市基盤を整備し、まちづくりを進めています。
京都府内でも多くの自治体が、都市計画税を導入しており、近隣でも長岡京市では昭和39年から、向日市では昭和43年から都市計画税を導入しています。
大山崎町では、主として町内企業からの豊かな税収を背景に、都市計画税を課税することなく、まちづくりを行ってきました。しかし、近年ではピーク時と比べると10億円以上の減収となっており、また、町民税法人税割は景気動向に左右されやすく不安定であることに加え、本格的な少子高齢・人口減少時代を迎えた中においては、今後の税収の増加は見込みにくい状況にあります。その一方で、社会保障関連経費、公共施設の老朽化対策、災害対策などの財政需要が増大しています。
このような中で、将来のまちづくりを見据えたときに、安定した財源の確保は10年以上前から大きな課題となっており、かねてからこの都市計画税の導入に向けた検討を進めてきました。
この間、平成25年以降、都市計画税の導入に関連する議案を計3回町議会へ提案してきましたが、いずれも導入に至らなかった経過があります。その後も都市計画税導入の必要性については、町議会において議論を重ねてきましたが、今般の平成29年町議会第3回定例会において、関連議案を再度提案。賛成多数で可決され、都市計画税を導入することとなりました。
なお、この間の町民の皆様からのご意見やご要望を踏まえた中で、農地への課税に関しては、平成25年度から、市街化区域内の農地の保全を図ることを目的とした生産緑地制度を導入しました。また、国民健康保険税の課税に関しては、平成26年度から、固定資産に対して課税される資産割を廃止しました。
今回の都市計画税の再提案では、こうしたこれまでの経過を踏まえ、あわせてご指摘をいただいていた使途の明確化を図り、それに見合う税率を設定し、加えて適正管理のための基金も設置したうえで提案し、可決されました。
2.町の行財政運営の状況
(1)現状と課題
町は平成29年度、町制施行50周年を迎えました。町制施行前の昭和40年に4千人弱だった町の人口は、昭和50年には現在とほぼ同じ約1万5千人と急激に増加しました。それに伴って当時整備したインフラ資産を含む公共施設の老朽化対策が、現在、町の大きな課題となっています。
また、昨今の気象変動の影響で、全国的に豪雨が頻発していますが、大山崎町においても、数度にわたって豪雨による内水氾濫の被害が発生しています。
このような中、将来にわたって町民の皆さんの
○命と暮らしを守り、いっそうの笑顔が生まれるまちづくりを進めるためには、安心安全の確保がとりわけ重要となっています。
○安心安全な暮らしを維持していくためには、公共施設の老朽化対策や災害対策などあらゆる基盤整備に取り組むことが重要となっています。
さらに昨今は、全国的に少子高齢化が進展していますが、本町も決して例外ではなく、医療費や介護費など社会保障関連経費の負担は年々増加しており、ますます進展する少子高齢化対策などのソフト面での対応も迫られています。
一方で、歳入の根幹となる町税については、法人からの税収、特に町民税法人税割では昭和60年のピーク時と比べると10億円以上の減収となっています。さらに、町民税法人税割は景気動向に左右されやすく、不安定な状況が続いています。また、今後も、人口減少社会において、税収の増加は見込みにくい状況にあります。
(2)行財政改革の状況
この間、財政状況が厳しい中、町では不断に行財政改革を行ってきました。
中でも、職員数の削減には特に積極的に取り組んでおり、平成18年度~平成21年度にかけての集中改革プラン期間中の職員数の削減率は、京都府内一となっており、それ以降も定員管理の適正化に努めています(平成17年度173名→平成28年度134名)。また、独自の給与減額措置の実施や諸手当の見直しなど、人件費総額の大幅な削減を行っており、集中改革プラン取り組み前と平成28年度の単年度の比較では、約2.8億円の減額となっています。なお、集中改革プランに取り組み始めてから平成28年度にかけての人件費総額の削減額は合計で約33億円となります。
さらに、長寿苑、なごみの郷の指定管理委託や、JR山崎駅前駐輪場、第3保育所の給食調理業務の民間委託や駅前駐車場の民営化、あわせて町有地売却なども推し進め、一定の財政効果を生んできました。
また、近年では、町のPR活動による観光入込客数・観光消費額の増加、町内の空き店舗等への事業者の進出、国・府の補助金の積極的な獲得、ふるさと納税制度の活用などを進め、積極的に歳入確保に努めています。
3.都市計画税の概要
(1)使途
都市計画税は、法定の目的税です。地方税法に基づき、各自治体で条例を制定し課税するもので、その使途は、法律で、都市計画法に基づいて行う都市計画事業等に限定されています。都市計画事業等とは、都道府県知事の認可を受けて、良好な都市環境を確保することなどを目的として、道路等の交通施設、上下水道施設、教育文化施設等を整備する事業等のことです。町が現在実施している都市計画事業等は、主に公共下水道事業であり、都市計画税の課税に伴う税収は、その事業費用に充てることになります。
具体的には、雨水処理のための雨水排水ポンプ場の排水能力強化・改築や、汚水処理のための汚水中継ポンプ場や汚水管の耐震化や老朽化対策に要する費用に充て、安心・安全な生活基盤を整備します。
(2)納税義務者
都市計画税の納税義務者は、賦課期日である各年1月1日時点での、大山崎町内の市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者です。平成30年度分の都市計画税の場合、平成30年1月1日が賦課期日となります。
なお現在、大山崎町内のほぼ全ての住宅が、市街化区域内に所在しています。
(3)税率と収入見込額
都市計画税の税率は、制限税率(0.3%)の範囲内で、各自治体での都市計画事業等の実施状況等を踏まえ、議会での議決を得て設定することとなりますが、今回の導入にあたって、当面の都市計画事業等に要する費用を精査した結果、0.1%と設定しています。
現在、町が実施している公共下水道事業には、公費(一般財源)で負担する額として、年間約1億円が必要となっています。この約1億円に相当する額を都市計画税で賄うことを予定し、税率を0.1%と設定したもので、これにより、平成30年度は総額で約9,700万円の収入を見込んでいます。
(4)基金の設置
都市計画事業等の進捗状況により、都市計画税に残余が生じた場合には、今回新たに設置する「都市計画事業基金」に積み立てを行い、適正に管理します。基金に積み立てを行った都市計画税は、翌年度以降の都市計画事業等に限定して使用します。
(5)税額の算出方法
都市計画税額の算出式は、次のとおりです。
都市計画税額=課税標準額×税率(0.1%)
※課税標準額は市街化区域内の土地・家屋の固定資産の評価額ですが、住宅用地の特例措置等の適用があります。詳しくは、固定資産税(土地・家屋)をご覧ください。
モデルケース
※固定資産の評価額は、土地及び家屋の面積に対して一律に決定するものではなく、下記はあくまでも参考の金額です。
|
例示 |
面積等 |
都市計画税 (年税額) 税率0.1% |
|
一戸建て (木造・築10年程度) |
土地 100平方メートル |
3千円 |
|
家屋 90平方メートル |
5千円 |
|
|
(合計) |
8千円 |
|
|
円明寺が丘団地テラスハウス (鉄筋コンクリート2階建・築45年超) |
土地 120平方メートル |
4千円 |
|
家屋 90平方メートル |
1千円 |
|
|
(合計) |
5千円 |
|
|
円明寺が丘団地マンション アルファベット棟 (鉄筋コンクリート4階建・築50年超) |
土地 85平方メートル |
3千円 |
|
家屋 55平方メートル |
1千円 |
|
|
(合計) |
4千円 |
|
|
月極駐車場 |
土地 500平方メートル |
3万2千円 |
|
農地 (市街化区域) |
土地 1,000平方メートル |
2万円 |
|
農地 (市街化区域の生産緑地) |
土地 1,000平方メートル |
1千円未満 |
(6)納税方法
都市計画税額は、固定資産税とあわせて納めていただきます。
納税者の方には、固定資産税・都市計画税納税通知書が送付されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税住民課 税務係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年08月18日