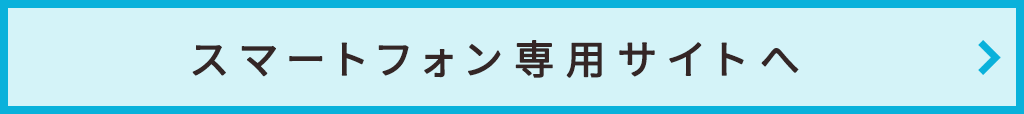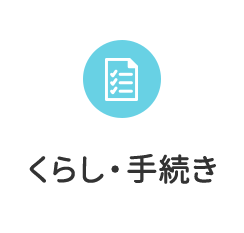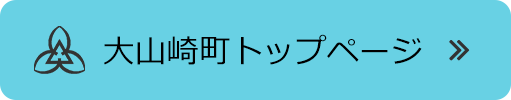子どもの定期予防接種(令和7年4月1日更新)
定期予防接種
- 定期予防接種の接種期間を過ぎると、任意予防接種(全額自費)になります。任意予防接種は予防接種法に基づく予防接種ではありません。
- 個別予防接種は、こどもの予防接種協力医療機関で事前に予約をしてください。接種の際には、親子健康手帳と町が発行する予診票を持参してください。
- 個別予防接種は、原則として保護者の付き添いが必要です。保護者以外の方が付き添う場合は、委任状を持参してください。(13歳以上の特例対象者の日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種では、前もって保護者の同意と署名があれば、保護者の付き添いがなくても接種できます。)
- 転入してきた方、予診票を紛失された方は、親子健康手帳を持参のうえ、健康増進係で予診票の発行をうけてください。
- 予防接種協力医療機関以外の京都府内の医療機関で接種を希望される場合は、必ず事前に健康増進係までご連絡ください。
個別接種
下記のこどもの予防接種協力医療機関で接種してください。
ロタウイルスワクチン
ワクチンの種類によって対象年齢や接種回数等が違います。
対象年齢
| ロタリックス | 生後6週0日から24週0日後まで |
| ロタテック | 生後6週0日から32週0日後まで |
(予診票は生後2か月になる月初めに送付します。)
接種回数と接種方法
初回接種の標準的接種期間は生後2か月から出生14週6日後までに経口接種します。
| ロタリックス | 27日以上の間隔をあけて2回接種します。 |
| ロタテック | 27日以上の間隔をあけて3回接種します。 |
B型肝炎
対象年齢
1歳誕生日の前日まで(母子感染予防として出生後に抗HBs人免疫グロブリンの投与とB型肝炎ワクチンを接種した児は対象外です。予診票は生後2か月になる月初めに送付します。)
接種回数と接種方法
標準的な接種期間は、生後2か月から9か月に至るまでに3回接種します。
1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目を接種します。その後、1回目の接種から139日以上、かつ、2回目の接種から6日以上の間隔をおいて3回目を接種します。
小児の肺炎球菌感染症(小児用肺炎球菌感染症)
対象年齢
生後2か月になる前日から5歳(誕生日の前日)まで(予診票は生後2か月になる月初めに送付します。)
接種回数と接種方法
接種を開始する月齢、年齢により、接種回数が異なります。
1.2か月になる前日から7か月になる前日までに接種を開始する場合(4回接種)
- 初回接種は、27日以上の間隔をおいて3回(標準的には、1歳までに27日以上の間隔をおいて、3回)
- 追加接種は、3回目終了後60日以上の間隔をおいて1歳以降に1回(標準的な接種年齢は、1歳から1歳3か月)
2.7か月から12か月になる前日までに接種を開始する場合(3回接種)
- 初回接種は、27日以上の間隔をおいて2回(標準的には、1歳までに27日以上の間隔をおいて、2回)
- 追加接種は、2回目終了後60日以上の間隔をおいて、1歳以降に1回
3.1歳の誕生日から2歳(誕生日の前日)までに接種する場合(2回接種)
- 60日以上の間隔をおいて2回
4.2歳の誕生日から5歳(誕生日の前日)までに接種する場合(1回接種)
- 1回
ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・Hib感染症(ヒブワクチン)(五種混合ワクチン)
対象年齢
生後2か月になる前日から7歳6か月になる前日まで(予診票は生後2か月になる月初めに送付します。)
接種回数と接種方法
- 4回接種します。
- 第1期初回接種は、生後2か月〜生後7か月に至るまでに開始し、20日以上の間隔をおいて3回(標準的には20日から56日までの間隔をおいて)
- 追加接種は、初回接種終了後、6か月以上の間隔をおいて1回(標準的には初回接種終了後6か月から18か月までの間隔をおく)
注意
既にHib感染症(ヒブワクチン)や四種混合ワクチンを1回以上接種された方は、原則として過去に接種歴のあるワクチンと同一ワクチンを接種します。(五種混合ワクチンへの変更は必要ありません。)
ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ(四種混合ワクチン)
対象年齢
生後2か月になる前日から7歳6か月になる前日まで(予診票は生後2か月になる月初めに送付します。)
接種回数と接種方法
- 4回接種します。
- 初回接種は、20日以上の間隔をおいて3回(標準的には20日から56日の間隔で3回)
- 追加接種は、初回3回目終了後、6か月以上の間隔をおいて1回(標準的には初回3回目終了後12か月から18か月の間に1回)
注意
生ポリオワクチンおよび不活化ワクチンを4回接種された方(7歳6か月になる前日まで)で、3種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)ワクチンが4回完了していない方は、健康増進係にご相談ください。
《四種混合ワクチンについての大切なお知らせ》
令和6年4月から五種混合ワクチン(四種混合にHibワクチンを追加したもの)が定期接種ワクチンの対象となったことから、四種混合ワクチンが製造販売中止になりました。お子さんの親子健康手帳をご確認のうえ、四種混合ワクチンが4回完了していない場合は、在庫がある間にお早めの接種をお願いいたします。
法律上は、四種混合第1期追加接種は、第1期初回3回目の接種終了から6ヶ月あいていれば受けることができます。
※基本的には『同一ワクチンで接種完了すること』とされていますが、ワクチンがないなどやむを得ない事情がある場合は、五種混合に切り替えて接種を受けることが可能です。ただし、その際は四種混合ワクチンとヒブワクチンそれぞれの接種回数により、切り替え出来ない場合もありますので注意が必要です。
例)
| これまでの接種歴 | 今後の対応 |
| 四種混合およびヒブワクチンを初回接種として3回実施 | 第1期追加接種として五種混合に切り替えて接種可能 |
|
四種混合を3回接種していて、ヒブワクチンは4回完了している |
五種混合に切り替えて接種することはできません。(ヒブワクチンが過剰接種になるため) |
※五種混合に切り替えて接種を受けられる場合は、お手元の四種混合ワクチン・ヒブワクチンの予診票と親子健康手帳を持参のうえ、役場1階5番窓口へお越しください。
Hib感染症(ヒブワクチン)
対象年齢
生後2か月になる前日から5歳(誕生日の前日)まで(予診票は生後2か月になる月初めに送付します。)
接種回数と接種方法
接種を開始する月齢、年齢により、接種回数が異なります。
1.2か月になる前日から7か月になる前日までに接種を開始する場合(4回接種)
- 初回接種は、27日(医師が必要と認めた場合は、20日)以上の間隔をおいて3回
(標準的には、1歳までに27日以上56日の間隔をおいて、3回) - 追加接種は、3回目終了後7か月以上の間隔をおいて1回
(標準的には初回終了後7か月から13か月の間に1回)
2.7か月から12か月になる前日までに接種を開始する場合(3回接種)
- 初回接種は、27日(医師が必要と認めた場合は、20日)以上の間隔をおいて2回
(標準的には、1歳までに27日以上56日の間隔をおいて、2回) - 追加接種は、2回目終了後7か月以上の間隔をおいて1回
(標準的には初回終了後7か月から13か月の間に1回)
3.1歳から5歳(誕生日の前日)までに接種する場合(1回接種)
- 1回
麻しん風しん
対象年齢
- 1期は、1歳(誕生日の前日)から2歳(誕生日の前日)まで(予診票は、乳児後期健診時に手渡しします。)
- 2期は、就学前の1年間(予診票は、小学校入学前の年度初めに送付します。)
接種回数と接種方法
1期に1回、2期に1回接種します。
麻しんまたは風しんのいずれかにかかった場合でも、麻しん風しん混合ワクチンを使用することが可能とされています。
《MR(麻しん風しん混合)ワクチンに関する大切なお知らせ》
令和6年度に生じたMRワクチンの偏在により、接種を希望した方が受けられなかった状況をふまえ、下記対象者に限り、令和7年4月1日〜令和9年3月31日までの2年間、接種期間を延長することが決まりました。
●対象者
| 第1期 |
令和6年度内に2歳に達した小児 |
| 第2期 |
令和6年度に年長の学年であった小児 |
●接種を受ける流れ
上記対象者の方は、新しい予診票をお渡ししますので、親子健康手帳とお手元のMRワクチン予診票を持参のうえ、役場1階5番窓口へお越しください。有効期限が切れた予診票は使用できません、ご注意ください。
水痘(みずぼうそう)
対象年齢
1歳(誕生日の前日)から3歳(誕生日の前日)まで(予診票は、乳児後期健診時に手渡しします。)
接種回数と接種方法
- 1回目は、標準的には1歳から1歳3か月までの間に接種
- 2回目は、1回目接種後、3か月以上の間隔をおいて接種(標準的には、1回目接種後、半年から1年の間に接種)
注意
過去に水痘の予防接種を1回接種した場合と、2回接種したがその間隔が3か月未満の場合は、残りの1回を3歳までに接種することができます。過去に水痘にかかった場合は、受けられません。
日本脳炎
日本脳炎の予防接種は、副反応の事例があったことにより、平成17年度から21年度まで、積極的勧奨を行いませんでしたが、その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎予防接種を通常通り受けることができます。平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方は、日本脳炎の接種を受けることができます。接種を希望される方は、接種をする前に母子健康手帳を持って、健康増進係まで予診票の発行手続きにお越しください。
平成19年4月2日以降に生まれた方
接種方法は以下のとおりです。
第1期
対象年齢は、生後6か月から7歳6か月の前日までです。(標準的には3歳から4歳)3回接種します。(予診票は4月1日時点で3歳の子に対して年度初めに送付します。) 初回接種は、6日以上の間隔をおいて2回(標準的には6日から28日の間隔で2回) 追加接種は、初回2回目終了後6か月以上の間隔をおいて1回(標準的には初回2回目接種後おおむね1年後に1回)
第2期
対象年齢は、9歳から13歳誕生日の前日までです。(標準的には9歳から10歳)1回接種します。(予診票は小学4年生になる年度初めに送付します。)
平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方
対象年齢は、第1期、第2期ともに20歳誕生日の前日までです。
第1期
- 第1期を3回とも受けていない人は、6日以上(標準的には6日から28日)の間隔をおいて2回接種、初回2回目接種終了後、6か月以上(標準的にはおおむね1年後)の間隔をおいて1回
- 第1期を1回受けた人は、6日以上の間隔をおいて2回接種
- 第1期を2回受けた人は、1回接種
第2期
1期終了後、6日以上の間隔をおいて(1期終了後、おおむね5年以上の間隔をおいて接種することが望ましい)接種します。
ジフテリア・破傷風(第2期)
対象年齢
11歳(誕生日の前日)から13歳(誕生日の前日)まで(予診票は11歳になる翌月に送付します。)
接種回数
1回接種します。
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)
対象年齢
小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女子(予診票は中学1年生になる年度初めに送付します。)
接種回数と接種方法
子宮頸がんワクチンは、3種類(2価ワクチン、4価ワクチン、9価ワクチン)あります。原則、接種完了まで同じワクチンを接種します。
- 2価ワクチンを受ける場合 1回目から1か月以上あけて2回目を接種、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて3回目接種(標準的には、1回目から1か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目)
- 4価ワクチンを受ける場合 1回目から1か月以上あけて2回目接種、2回目から3か月以上あけて3回目接種(標準的には、1回目から2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目)
- 9価ワクチンを受ける場合
<小学6年生から14歳の場合は2回接種>
1回目から6か月あけて2回目接種
(1回目から5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。)
<15歳以上の場合は3回接種>
1回目から2か月あけて2回目接種し、1回目から6か月以上あけて3回目接種
●HPVに関する詳細は下記ご参照ください。
厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症〜子宮頸がん(しきゅうけいがん)とHPVワクチン〜 )《外部リンク》
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種 キャッチアップ
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種は、接種部位以外の身体の広い範囲で持続する疼痛の副反応症例等について十分に情報提供できない状況にあったことから、積極的な勧奨を一時的に差し控えられていました。しかし、令和3年11月12日に開催された専門家の会議において、安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、令和4年4月から積極的勧奨を再開しています。
積極的勧奨が差し控えられていた期間に接種対象年齢を過ぎてしまった方に公平な接種機会を確保するため、キャッチアップ接種が開始されました。
●HPVキャッチアップ接種に関する詳細は下記ご参照ください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~《外部リンク》
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_catch-up-vaccination.html
対象
平成9年4月2日〜平成21年4月1日生まれの女性で過去にHPVワクチン3回完了していない方
接種回数と接種方法
上記「ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)」をご参照ください。
実施期間
令和7年3月31日まで
※注意事項※
・過去の接種記録はご自身の親(母)子健康手帳をご確認ください。
・接種期間終了間際(令和7年3月31日)には、再びワクチン需要が増加するおそれがあります。接種開始を検討されている方はお早めにご予約ください。
★経過措置についてはこちら(令和7年2月10日)
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種のキャッチアップ接種経過措置について(令和7年2月10日掲載)
集団接種
BCG
対象年齢
1歳(誕生日の前日)まで(予診票は赤ちゃん訪問時に手渡しします。)
接種回数と接種方法
標準的には、生後5か月になる前日から8か月までに1回接種します。
接種場所
大山崎町保健センター
接種日時
赤ちゃん訪問の際に、ご案内します。下記の「保健センター年間計画表」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康課 健康増進係
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-4161
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日